Staking/GOX PRO
Fluid Protocolレポート- 流動性の統合による資本効率改善の仕組みと戦略を概観
投稿日 2025年 04月 17日
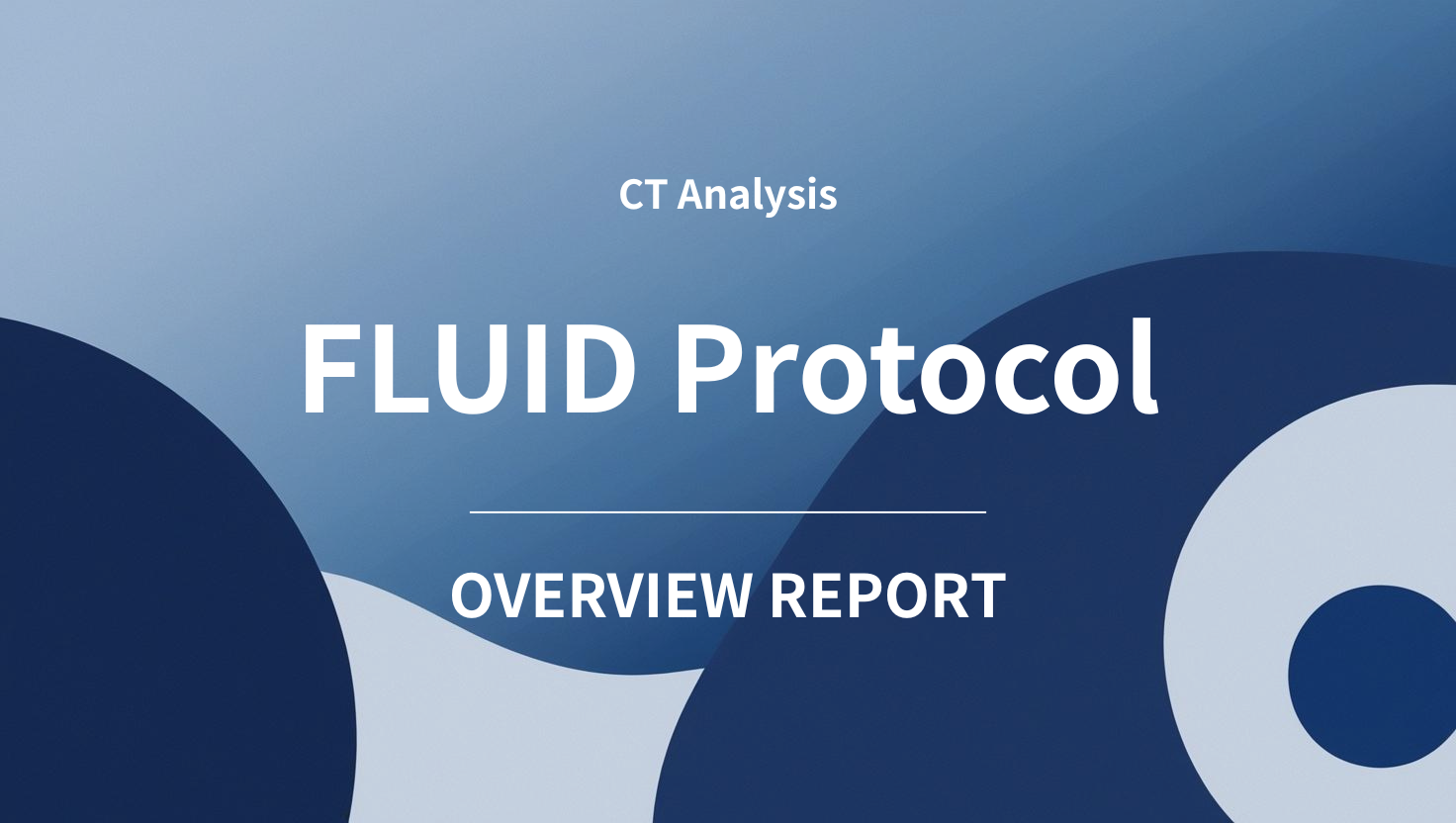
目次
※読者の皆様により多くの情報と分かりやすい解説をすばやくお届けするため、本レポートの図表作成には、一部AIを使用しています。筆者による査読済みであるものの、一部事実とは異なる表記等がある可能性がありますが、ご了承ください。
Fluidは、DeFi(分散型金融)の資本効率と流動性管理に変革をもたらす次世代プロトコルです。2023年10月に最初のコンセプトが発表され、現在ではEthereum、Arbitrum、Base、Polygonの4つのブロックチェーンに展開され、積極的なマルチチェーン戦略を推進しています。
Instadappチームによって開発されたFluidは、革新的な「Liquidity Layer」を基盤とし、レンディングプロトコルとDEX(分散型取引所)を統合することで、従来のDeFiプロトコルが直面していた資本効率の課題を解決する設計を特徴としています。
中でも注目すべきは「Smart Debt」と「Smart Collateral」という概念です。従来なら担保や債務としてロックされる資産を取引流動性として活用することで、Fluid DEXは1ドルのTVL(Total Value Locked)あたり最大39ドルの流動性を生み出すとされています。
AaveやCompoundなどの既存レンディングプロトコル、またUniswapやCurveといった主要DEXとの競合の中で、Fluidはその革新的な設計と高い資本効率によって差別化を図っています。DeFiの進化を象徴する例として、今後のDeFiエコシステムにおいて中心的な役割を担う可能性を秘めています。
イントロダクション
DeFi市場の現状と課題
DeFi(分散型金融)は、仲介者を介さずに金融サービスを提供するブロックチェーン技術の先端的応用として、ここ数年で急速に成長してきました。レンディング、借入、取引、ステーキングなどの伝統的な金融サービスをブロックチェーン上に実装することで、DeFiは金融の民主化と効率化を推進しています。
しかし市場拡大に伴い、資本効率の問題が鮮明になりました。従来のDeFiプロトコルでは、異なるプロトコル間で資本が分断されがちで、同じ資産を複数の場所で効率的に活用することが難しい状況でした。たとえばAaveにETHを預けた場合、そのETHをUniswapなどのDEXで同時に流動性提供に活用することはできません。こうした資本の分断がDeFiエコシステム全体の効率性低下を招いていたのです。
また、DEXやレンディングプロトコルが乱立したことによる流動性の断片化も問題視されています。各プロトコルに流動性が分散し、特に市場変動時には流動性不足によるスリッページ拡大や取引失敗などが起こりやすくなっていました。
さらに、操作の複雑さやガス代の高さなど、ユーザー体験面のハードルも依然として課題です。こうした多面的な制約によって、DeFiが大規模に普及する上での障壁となっていました。
Fluidプロトコルの誕生背景
こうした課題を解決するため、Instadappチームは2023年にFluidプロトコルを立ち上げました。Instadappは2018年からUniswap、Aave、Curve、Makerなど数多くのDeFiプロトコル上にソリューションを構築してきた経験を活かし、DeFiのスケーラビリティを阻害する根本的な問題を特定。これを打破するビジョンとしてFluidが創設されました。
Fluidの核心アイデアは、あらゆる資産の流動性を統合管理する「Liquidity Layer(流動性レイヤー)」を構築し、その上にレンディングとDEXを統合する設計です。こうして資本の分断を解消し、流動性を効率的に活用する狙いがあります。
特に「Smart Debt(スマート債務)」と「Smart Collateral(スマート担保)」の導入は革新的で、債務と担保そのものを取引流動性として活用できる点が、既存のDeFiにはない大きな特徴となっています。
Fluid Protocolの概要

| 項目 | 概要 |
|---|---|
| プロジェクト名称 | Fluid Protocol |
| ローンチ年月 | 2023年10月 |
| 開発企業 | Instadapp |
| 創設者 | Sowmay Jain(Instadapp の共同創設者兼 CEO)および Samyak Jain(共同創設者) |
| 公式X URL | https://x.com/0xFluid |
| 公式Discord URL | https://discord.com/invite/C76CeZc |
| 公式ウェブサイト URL | https://fluid.io/ |
Fluidは、DeFiの資本効率と流動性管理を抜本的に再定義する革新的なアーキテクチャを採用しており、その中核に位置するのがLiquidity Layerです。このレイヤーを基盤にして、以下の3つの主要コンポーネントが密接に統合されています。
- Liquidity Layer:あらゆる資産の流動性を統合管理する基盤レイヤー
- レンディングプロトコル:貸出と借入の機能を提供
- DEXプロトコル:分散型取引所の機能を提供
これらのコンポーネントはサイロ化(孤立)せず、Liquidity Layerを介して流動性を共有するため、1つの資産が担保・借入・流動性提供など複数の用途で同時に活用できます。結果として、大幅な資本効率の向上が期待されています。
さらに、このLiquidity Layer上にモジュール的な安全性ルールが設けられており、特定の資産から複数の利回りを獲得するための仕組みも備えています。こうした「流動性の共有設計」が、既存のDeFiプロトコルにはないFluidの大きな特徴と言えます。
Liquidity Layerの概要と特徴
Liquidity LayerはFluidエコシステムの要となるコンポーネントで、すべての資産の流動性を一括管理し、上位のレンディングやDEXといったプロトコルに対して流動性を供給します。以下は主な特徴です。
この続きを読むには
この記事は会員限定の記事になります。
登録すると続きをお読みいただけます。
タグ
DeFi
Ethereum
Layer2
お問い合わせはこちら
専門的なリサーチャーのリサーチしてほしい内容がある
新規事業のアイディア出しからコンサルティングしてほしい
その他、ブロックチェーン事業に関する全般的な相談をしたい
